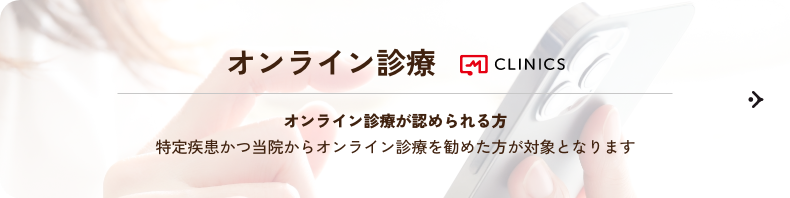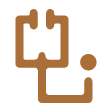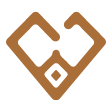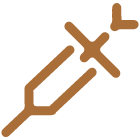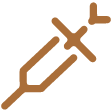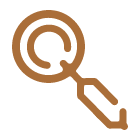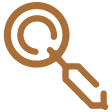- 2024.04.20お知らせ 【必ずお読みください】新型コロナウイルス対応について ※2024年4月20日更新
- 2024.04.02お知らせ 2024年4月・GW期間中のお休みのお知らせ
- 2024.03.19お知らせ 医療事務(正社員)の募集を開始しました
1週間以内に発熱や咳、
かぜの症状のある場合は
必ず事前にお電話ください。
当院では発熱や咳などのかぜ症状のある方の診察は、感染防止のためその他の疾患で通院されている方々と待機場所を分けており、「完全予約制」で対応いたします。来院前の検温にご協力をお願いいたします。
お電話が繋がりにくい状況がございます。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。風邪症状や発熱症状の方の直接のご来院はお控えください。
お電話にてご予約お願いします。


- 発熱状況によっては個室または通常の診察室で診察いたします。
- 検査内容は当院にて判断させていただきます。
- 風邪症状の方は事前にご予約ください。
- 当院からのご案内についてはLINEでも発信
しています。
よろしければご登録ください。
こちらから


診療内容について
大きな病気にかかってからの治療では手遅れになってしまうケースもあります。その前段階でアプローチすることで、未然に防げる病気が増えてきました。
病気になると心身ともに辛く、周りの方も心配されます。通院できる範囲で構いませんので、定期健診や日々の生活習慣などを見直し、病気予防を一緒におこなっていきましょう。
RECRUITご応募をご検討中の方へ
働くことが楽しい、そう思える職場だからこそ、患者さんや周りのメンバーにも、優しく親切にできる。
働く環境はみんなで良くしていくもの。そんな働き方を全員で作っているクリニックです。大切にしている考え方や各職種の働き方、募集要項を掲載しています。
ご応募お待ちしております。